


東海道五十三次、宿場町のひとつ原宿。その原にある庭園の物語。
沼津、原地区で長く愛される歴史ある庭園へ。





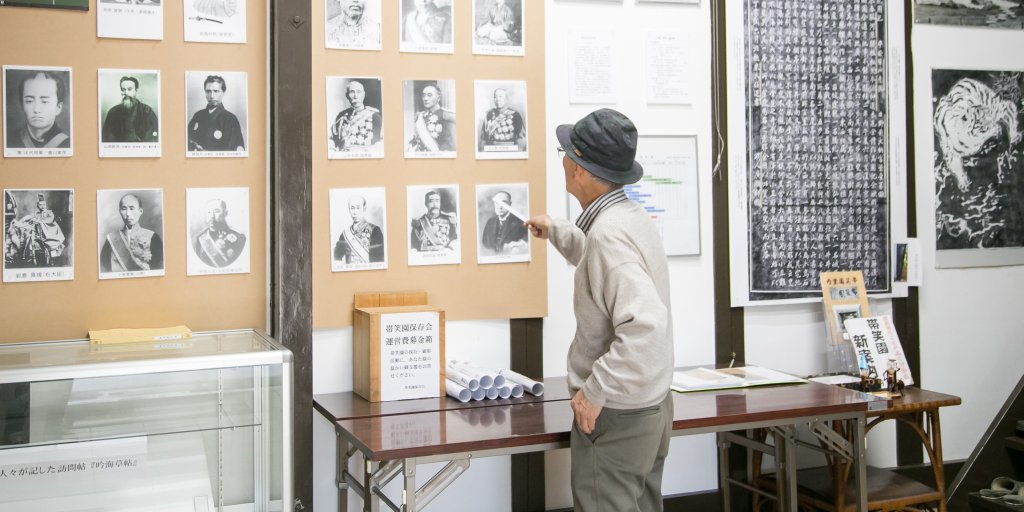





















芍薬

牡丹

ミツガシワ

蓮・水蓮

椿

シジュウカラの卵


沼津市在中 日々の写真を撮っています。
現御当主の植松さん!
お散歩しながらのご案内ありがとうございました。
花の話に、絵の話。話始めるといくら時間があっても足りない!
と、楽しい時間をありがとうございました。
蓮の花が咲く頃にまた伺います。